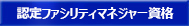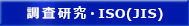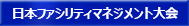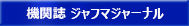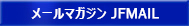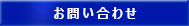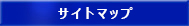�e�l�̎d���Ƃ�
�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�̗̈�͂ƂĂ��L���A���̑Ώۂ��g�債�Ă���A�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[���������Ă����Ƃ�c�̂̋Ǝ�⎖�ƁA�S���Ɩ�������ɂ킽��܂��B�t�@�V���e�B�}�l�W�����g��S���Ɩ��Ƃ��Ă�����F�l�ɁA���d����FM�ւ̎v��������Ă��������܂����B
�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�̎d���Ƃ͉����H�l�X�Ȏ��_�����FM�̑��l���≜�[���������Ă��������A�F����̋Ɩ��ɐ����p���������B
�����t�@�V���e�B�}�l�W�����g�̎��i�`�u�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[���i�v����
FM�Ɍg��邷�ׂĂ̕���ΏۂɕK�v�Ȑ��m���E�\�͂ɂ��Ď������s���A���i�҂͓o�^���邱�ƂŁu�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[���i�v���擾�ł��܂��B
FM�֘A�m���������ɂ͂悢�@��ƂȂ�܂��B2025�N�x���y�ю��i�o�^�����₷���Ȃ�܂��B���̋@��Ɂu�t�@�V���e�B�}�l�W���[���i�v�ɒ��킵�Ă݂܂��H
�ɂ��Ă͈ȉ��̃y�[�W�ł����ē����Ă���܂��̂ŁA�Q�l�ɂ������������B
�E�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[(CFMJ) ���i �����ē�
�@
�@
�@
FM�Ɍg��邷�ׂĂ̕���ΏۂɕK�v�Ȑ��m���E�\�͂ɂ��Ď������s���A���i�҂͓o�^���邱�ƂŁu�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[���i�v���擾�ł��܂��B
FM�֘A�m���������ɂ͂悢�@��ƂȂ�܂��B2025�N�x���y�ю��i�o�^�����₷���Ȃ�܂��B���̋@��Ɂu�t�@�V���e�B�}�l�W���[���i�v�ɒ��킵�Ă݂܂��H
�ɂ��Ă͈ȉ��̃y�[�W�ł����ē����Ă���܂��̂ŁA�Q�l�ɂ������������B
�E�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[(CFMJ) ���i �����ē�
�@
�@
�@
�t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎d���ɂ��ā@�`�F�l����̐�
�� �ȉ��̓��e�́AJFMA�@�֎��uJFMA�W���[�i�� NO.216 2024 AUTUMN�v�Ɍf�ڂ���Ă�����e������p���Ă���܂��BJFMA�W���[�i���́AJFMA����̊F�l�ɖ����Ŕz�z���Ă���ق��A���Ѓy�[�W ![]() ��������w���ł��܂��B
��������w���ł��܂��B

�� ���m �����v�R���X�g���N�V�����E�}�l�W�����g������� |
�u�l�E�g�D�E�Љ�ւ̍v���v��ڎw����FM
�@FM �̑��l�����i��ł���B���m�ɂ́u�{�݊Ǘ��v�Ƃ����������̌Œ�T�O����A�u�t�@�V���e�B���{�݂Ƃ��̊��v�Ƃ����{����FM �̒�`�̎����͈͂܂ŔF�m���ǂ��t���Ă����A�ƍl���Ă���B �@���́A���z�̃}�l�W�����g�E�R���T���e�B���O��Ђł�������v�R���X�g���N�V�����E�}�l�W�����g�� Strategy & Design Management �Ƃ�������ɏ������Ă���B���̎��ƕ��ł́u�����炵���������Ō��C�ȓ��{����낤�v�Ƃ����X���[�K���̂��ƁA�o�c�ڕW�̌��zPJ�̉^�c�Ƃ����A��ォ��쉺�܂ł��Ȃ���т������[�N�v���C�X�R���T���e�B���O�T�[�r�X����Ă���B���̔w�i�ɂ́A��ƂɂƂ��đ傫�ȓ����ƂȂ錚�z�v���W�F�N�g���A�o�c�ڕW��{�݉^�c�Ƃ̊|���Ⴂ�܂ܐi�߂��Ă��܂����Ƃւ̉ۑ�ӎ�������B �@�����ł�FM �̑��l������������A����ꂪ���g��2�̎�����Љ�����B ����(1)�b O3 ��エ���������I�t�B�X �@2023 �N5 ���ɂɃ��j���[�A���I�[�v���������Б��I�t�B�X�ł́A�������̕ϊv�����q�l�ɖ₤����Ƃ��āA�u���炪�ϊv�̃V���[�P�[�X�Ȃ�v�Ƃ����~�b�V�������f���A���ƕ��Ƃ��Đ헪�\�z����^�c�܂Ōg����Ă���B �@���݂̓I�t�B�X�̗��p���i�̂ق��A�ړI�ʂ�ɃI�t�B�X�����p����Ă��邩���j�^�����O���K�X�A�b�v�f�[�g���邽�߁A�R�~���j�P�[�V��������I�ȐE�\�Ƃ���Ј���O���ϑ��̃R�~���j�e�B�}�l�W���[�A��㏊���Ј��ɂ��C���t���G���T�[�i�ʏ�"���������������o�["�j�ō\������R�~���j�e�B�`�[���ɂ���āA�I�t�B�X�^�p�̌p���I�ȕ]���E�E���P�����{���Ă���B �@����ďI���łȂ��A�Ⴆ�ΎГ��O�C�x���g�〈�w�c�A�[�̊J�ÁAKPI �̃��j�^�����O�Ƃ������A���[�U�[��g�D�ւ̍v���ɂȂ���\�t�g�E�^�p�ʂ̎��g�݂��p�����邱�Ƃ��AFM �̏d�v�Ȏ��H�̈�ƂȂ��Ă���B ����(2)�b�^���[�J�[�I�t�B�X���j���[�A�� �@�^���[�J�[�̊e���_�̃��j���[�A���v���W�F�N�g�ł́A�ӎ����v�����[�N�X�^�C���^���[�N�v���C�X�R���T���e�B���O�Ɩ������H���Ă���B�^����ꂽ�������^�ꏊ�œ�����O�̂悤�ɓ����Ă����Ј��ɂƂ��āA�ւ�������Ď����I�ɓ������߂Ɂu�������^�����������l���A�ς��Ă����v�Ƃ����ӎ����v���K�v�ł������B �@��̓I�ɂ̓��j���[�A���ɕ����A�������^���[�N�v���C�X�ϊv��S���v���W�F�N�g���s�`�[���̗����グ��A�v���C�u�b�N�i�V�����I�t�B�X�Ŗڎw���������A�R���Z�v�g�A�g�������܂Ƃ߂��K�C�h�j�̍쐬�A����ɑS�Ђ̃I�t�B�X�������̊���܂Ƃ߂����[�N�v���C�X�K�C�h���C���̍쐬�ȂǁA�n�[�h�ʂ����łȂ��\�t�g�ʂ̎{��̎x�����s���A��Ƃ̃��[�N�X�^�C���ϊv�𑽗l�ȑ��ʂ���T�|�[�g���Ă���B �@2 �̎���ŋ��ʂ���̂́u�t�@�V���e�B��ʂ����o�c�����v���_�@�ɁA��i�ɔ���ꂸ��ƕϊv��o�c�ڕW�̎����̎x����ʂ��āu�l�E�g�D�E�Љ�ւ̍v���v��ڎw���Ă���_�ɂ���B �@��L����͂����鋳�ȏ��I��FM�̋Ɩ��͈͂����V�K�̈�̎��g�݂ł���A�ǂ�����u�l�E�g�D�E�Љ�ւ̍v���v�ɂȂ��邩�A�������Ȃ����ŕ�������͍����A���s����{��ɋ�Y������X���߂����Ă���B���������̘g�ɂƂ���Ȃ��������A�������g�̎������グ�AFM�̎˒����g���邱�ƂɂȂ���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������҂�����B �@���҂Ɗ���������Ȃ���AFM�̉\�����g���銈���ɍ����簐i���Ă��������B |

���R ���� ��������c�m�s |
�����Ԃ�ꏊ������Ƃ�������
�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�Ƃ̏o�� �@������Г��c�m�s��1910 �N�̑n�ƈȗ��A���q�l�̐��Y����n���������߂邱�Ƃɍv�����ׂ����܂��܂Ȏ��Ƃ��s���Ă��܂����B���݂ł́A�u�������ϊv�v�u�w�ѕ��ϊv�v�u��ƊX�Â���ϊv�v�̂R�̕ϊv�̎����Ɍ����AICT �Ɗ��\�z�̗��ʂ��A����ɂ킽��\�����[�V������p�������x�������Ă��܂��B���̒��ł������S�����Ă���̂́A�������ɑ���u�������ϊv�v�̂��x���ł���A���ɓs���̖����i�{���Ɂj�ɑ����\�z�̖ʂ���A���q�l�̐��Y����n���������߂邱�Ƃ�ړI�Ƃ����\�����[�V�����̔̔��A�c�Ɗ������s���Ă��܂��B�����̓������E������́A���܂��܂ȗ��R���疯�ԂƔ�ב傫���x��Ă���A�ߔN�̘J���l���̌������ł��̉ۑ�͂�茰���ɂȂ��Ă��Ă��܂��B���̂悤�ȎЉ��̒��A�����[�g���[�N����ActivityBased Working�� �̍\�z����ʂ��āA�����ł����̎d�����Љ�̖��ɗ��ĂƂ̎v���ŁA���X�����Ɏd���ɗ��ł���܂��B �@���āA���̂��d���̂��Љ�������Ă������������ŁA�Ȃ��F��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎��i���擾�����̂��A�ɂ��Ă��ȒP�ɐG�ꂳ���Ă��������܂��B���������͎��Ј��̈琬��ړI�Ƃ������̕��j����ł����B��i����́A���Ђ������N�A���Ȃ킿2 �N�ڂɕM�L�������A�����œ����m��������Ŋ������Ȃ���o����ς�ł����悤�ɂƂ̎w�����Ă��܂����B�����œ��Ђ��Ă����w�����K�C�h �t�@�V���e�B�}�l�W�����g�x����Ɏ������n�߂܂������A�Ȃɂ���o���s���̂��߁A�قƂ�ǂ̏͂ł܂Â��܂����̂ŁA�l��{�K���Ɏ��Ԃ��������Ă����Ǝv���܂��B�d�����C���[�W�����Ă��e�[�}�́u�m�I���Y�����x�����郏�[�N�v���C�X�̋����v��u���[�N�X�^�C�����x����ICT�v�ȂǂŁA�����đ����Ȃ��������Ƃ�����A�����A���i�擾�͍����ǂ̂悤�Ɏv���܂����B�������A�U��Ԃ��Ă݂�Ɗw�K���e�ɖ��ʂȂ��̂͂Ȃ��A���X�̎d���̒��ŁA���̎��ɕ������m���ɋ~��ꂽ���Ƃ��������������Ƌ����v���Ă��܂��B �v���t�F�b�V���i����ڎw���� �@������O�ł����A���q�l�́A�����A������̊��\�z�ɐ��ʂ����l���ł��邱�Ƃ�]��ł��܂��B�������u������̊��\�z�v�ƈꌾ�ł����Ă��A����ē��e�����I�t�B�X�ł̃��j���[�A���Ȃ̂��A�ړ]���j���[�A���Ȃ̂��Ȃǂɂ���āA���߂���m���̕��͈قȂ�A����o�������Ȃ����A�܂����̑S�Ă̒m�����K���ł��Ă���Ƃ͓��ꂢ���܂���B���̂悤�ȏŎ��Ɏ��M�������̂��A�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎��i�擾�̍ۂɊw�K�����m���ł��B���肪�������ƂɔF��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎��i�擾�ɂ͕��L���m�������߂��A���̒��ɂ͎��������̒��łԂ���ǂ����z���邽�߂̃q���g���������܂܂�Ă��܂��B���i�擾��A�w�����K�C�h �t�@�V���e�B�}�l�W�����g�x�����x���Ԃ������Ƃł��傤�B���Ƃ��ǂɂԂ������Ƃ��Ă��A�����Ԃ�ꏊ������Ƃ������Ƃ́A���̎��M�ɂȂ���A�����܂ō��܂��邱�ƂȂ��A�O�����Ɏd���Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł��Ă��܂��B �@��قǁA�u���q�l�́A����������̊��\�z�ɐ��ʂ����l���ł��邱�Ƃ�]��ł���v�Əq�ׂ܂������A���Ƃ��Ă��A�����������Ă���g�Ƃ��āA���̓��̃v���t�F�b�V���i���ƂȂ��悤�w�͂�ɂ��܂Ȃ�����ł��B�����邨�q�l�̐��ɉ�����ׂ��A���܂��܂Ȃ��ƂɃ`�������W���Ă����v���ŁA������t�@�V���e�B�}�l�W�����g�ɑ�����[�������ɓw�߂Ă܂���܂��B ���Ј��������I�ɋƖ����e��C���ɍ��킹�āA���ԂƏꏊ�����R�ɑI�����铭�����̂��� |

���c �D�� ������В|���H���X |
�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�ɂ��
���q�l�̊�Ɖ��l�����ڎw���� �@���͒|���H���X�̃��[�N�v���C�X�v���f���[�X�{���ɏ������Ă���B���q���܂̌o�c�ۑ肩�烏�[�N�v���C�X�헪���o���A�v���W�F�N�g�̊�悩��^�p�܂ň�т����R���Z�v�g�Ɋ�Â��R���T���e�B���O���s�����Ƃ��A��ȐE�����e�ł���B�܂��A�R���T���^���g�����̂܂ܐv�t�F�[�Y�E�{�H�t�F�[�Y�܂ŕ������Ȃ��炨�q���܂��x���ł���̂́A�������݉�ЂȂ�ł͂̓����ł���A���݂ł���Ƃ�����B �@�Ɩ��ɂ������ďd�v�Ȃ̂́A���[�N�v���C�X�\�z��ʂ��āA���q���܂̊�Ɖ��l�̌���ɏ����ł���^���邱�Ƃł���B���Y������A�̗p�͋����Ȃǎw�W�͂��܂��܂����A���炩�̌`�Ŋ�Ɖ��l�����߂郏�[�N�v���C�X����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߁A�P�Ɍ��h���̗ǂ���Ԃ�����̂ł͂Ȃ��A���[�U�[�Q���^�̃��[�N�V���b�v�Ȃǂ�ʂ��Đ��ݓI�ȃj�[�Y�������o���A����W�������S�[���E�R���Z�v�g�Ɋ�Â��āA���肽���p���������郌�C�A�E�g�쐬���̊�{�E���{�v����s�����Ƃ�S�����Ă���B �@���̈���ŁA�K�C�h���C���E�O�����h�f�U�C���쐬�Ȃǂ̊��i�K�݂̂ɎQ�����邱�Ƃ�����A���{�i�K�ɂďY��E���i�̒��B�E�[�i��ړ]�v�擙��PM �Ɩ������{���邱�Ƃ�����B����ɂ킽�郏�[�N�v���C�X�S�ʂ̉ۑ�ւ̑Ή����K�v�ƂȂ邤���A���q���܂̕����Ă���ۑ�����푽�l�ł��邽�߁A�v���W�F�N�g���ƂɈقȂ�v���Z�X�ƃS�[�����K�v�ɂȂ�B �@�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�i�ȉ��AFM�j�́A�w���̂��납��T�v�͔c�����Ă������̂́A��L�̂悤�Ȏ����̐E���ƌ��ѕt����܂łɂ́A�����ɔz������Ă��炵�炭�̎��Ԃ��K�v�������B �@�����A��L�̂悤�ȋƖ��̑��l������A���ʂ��Ďg����w�j���Ȃ������ׂĂ������ɁA��y�Ј�����w�����K�C�h �t�@�V���e�B�}�l�W�����g�x�i�ȉ��AFM �K�C�h�u�b�N�j��݂��Ă��炢�A���g�̋Ɩ��ɖ𗧂Ă�悤�ɂȂ����BFM �K�C�h�u�b�N�́AFM �Ɋւ���m�����ԗ��I�ɋL����Ă��邱�Ƃɉ����A���H�I�ȓ��e�ł���v���W�F�N�g�K�p�����₷�����߁A�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[���i�i�ȉ��ACFMJ�j���擾���Ȃ���������Q�l�Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ����������B����FM �̕]���w�W�ł���i���E�����E������3 �ڕW�Ƃ��̉��ʍ��ڂ́A�ۑ萮���̂��߂ɔ��ɖ𗧂w�W�ł��邽�߁A���݂��������j�Ƃ��Ċ��p���Ă���B �@�Ƃ͂����A�悭�g�����ڈȊO�ɑ��闝���͐������߁A��x�̌n�I�ɕ����悤�Ǝv���A�ꋉ���z�m�̎擾��ɁACFMJ �擾��ڕW�Ƃ����B���߂�FM �̈Ӌ`����w�ђ������ƂŁAFM ���o�c�����ł���Ƃ����O��ɗ����Ԃ邱�Ƃ��ł��A���[�N�v���C�X�\�z��ʂ��Ă��q���܂̊�Ɖ��l����Ɋ�^����Ƃ����ڕW���A���߂Ė��m�ɂ��邱�Ƃ��ł����B �@�܂��A�V�K�v���W�F�N�g�ɂ����ẮA�ێ��Ǘ��Җڐ������łȂ��A���[�N�v���C�X�ւ̓����Ό��ʂ𑪂�o�c�Җڐ����K�v�ł���B���i����Г��A�g������Ă���v�ҁE�{�H�҂̖ڐ��ɉ����A���q���ܑ��̎��_�����Ă�悤�ɂȂ����̂͑傫�Ȑi�����ƍl���Ă���B �@��ԍ\����C���e���A�̃f�U�C���ɗD�ꂽ���z��i�́A�ŏI�I�ɂ͂��ꎩ�̂��]�ƈ��̃��`�x�[�V������G���Q�[�W�����g����Ɋ�^���A��Ɖ��l�̌���ɂȂ���͂������Ă���Ɗm�M���Ă��邪�A���̉��l�͒�ʓI�Ȑ���������B����Ȓ��ŁAFM �̒m���E�v���Z�X�́A���܂��܂ȕ�������A�v���[�`���邽�߂̕���ƂȂ���e�ł���B �@������肩�璆���ƌĂ��N��ƂȂ��Ă������A���݁E�t�@�V���e�B�̐��E�͉��[���A�܂��܂��o���������Ƃ��Ȃ��Ɩ��������B�܂��A�������̕ω���[�N�v���C�X�̃g�����h�̕ϑJ�ƂƂ��ɁA�Ɩ��̑ΏۂƂȂ�̈悪�L�����Ă��邱�Ƃ������Ă���B�C���v�b�g�ƃA�E�g�v�b�g���J��Ԃ��Ȃ���AFM �̒m�������[�߂邱�ƂŁA����̉��l�����߂Ă��������B |

���{ ���� �听���݊������ |
��`�^�c���Ɠ��ɂ�����t�@�V���e�B�}�l�W�����g
�@���͌��݁A��`�̉^�c�����s���R���Z�b�V�������Ƃɏ]�����Ă���B��`�̃R���Z�b�V�������ƂƂ́APFI �@�i���Ԏ������̊��p�ɂ������{�ݓ��̐������̑��i�Ɋւ���@���j���Ɋ�Â��A�Ǘ��ғ��͖��Ԏ��Ǝ҂ɋ�`�������ԉ^�c���錠����ݒ肵�i�����{�ݓ��^�c����ݒ�j�A���⎩���̂͂��̑Ή��邱�Ƃ��w���B���Ђ͂���܂łɁA�S���̑����̋�`�Ɋւ��Đv�E���݂𒆐S�Ɍg����Ă������A����������̉^�c�Ɩ��ɂ����g��ł���B�����Â���Ɋւ�邠����t�F�[�Y�ɂ����ē��Ђ̑����͂����ׂ��A�R���Z�b�V�������Ƃ̎��g�݂�i�߂Ă���B �@��`�ł̓��X�̋Ɩ���1 �ɁA����Ȍ����̈ێ��Ǘ������܂܂��B���ɋ�`��365 ���ғ����Ă���A�l�X�̈ړ����x����d�v�ȃC���t���ł��邽�߁A�����̕s�����`�@�\�̌p���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����ꂪ����B����ɉ����l���̐l�X�����p���邽�߁A���Ɍ����̉e���ŋ�`���X�g�b�v���Ă��܂��ƁA�o�ϓI�A�Љ�I�ȑ��������ɑ傫���B���������邽�߂ɂ́A���S���S�Ȍ������ێ����邽�߂̃}�l�W�����g���d�v�ƂȂ邪�A���̒���1 �Ƀt�@�V���e�B�}�l�W�����g�̒m�������������ƍl����B �@���i�擾�O�́A�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�Ɋւ���m���͏��Ȃ��A�P�Ɂu�������ێ��Ǘ��E�L�����p���邽�߂̃m�E�n�E�v�Ƃ������x�̔F���ł����Ȃ������B�������A�����n�߂āA�e�L�X�g�ł���w�����K�C�h�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�x��ǂ�ł���ƁA�P�Ɍ����̈ێ��Ǘ���L�����p�����łȂ��A������ʂ����v���W�F�N�g�}�l�W�����g�\�͂̌���ɂ���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���A���i�擾�����B�Ⴆ�A�O�q�̃e�L�X�g�ɏo�Ă��铝���}�l�W�����g�Ɩ��́A��`�����S�E���S�E�~���ɉ^�p���邽�߂ɕK�v�ƂȂ�g�D�\�z��R�X�g�Ǘ����̍l�����ɂ����������Ƃ��ł��A����܂Ŕ��R�Ƒ����Ă����v���W�F�N�g�}�l�W�����g�Ɩ���̌^�I�ɗ������邱�Ƃ��ł����B���ݒS������Ɩ��₻�̃v���Z�X����P�Ȃ�C���[�W�Ŕc�����邾���łȂ��A���ꉻ���ė����ł���ƁA���̌����Ɋւ���l�����〈�������ς��ƍl����B �@���i�擾��́A���X�̋Ɩ��Ɏ��g�ޒ��ŁA�P�Ɍ��������ꂢ�ɕۂƂ������Ƃł͂Ȃ��A���̌����ێ���ʂ��ĎЉ�I�ɂǂ̂悤�ȈӋ`�≿�l�����邩�A�����Ă���������E�p�����邽�߂ɂ͂ǂ̂悤�ȍs���E�}�l�W�����g������ׂ����A�Ƃ����ӎ����������ꂽ�Ƃ��l����B���̂悤�Ȉӎ��������ƂŁA���O�Ɍ����̕s���������邱�Ƃɍv�����邾���łȂ��A���ɕs��������Ă���`�@�\�̌p���ɂ͎x�Ⴊ�Ȃ��悤�ɍŏ����̉e���ɗ}���邱�Ƃ��ł���ƍl����B������i�߂钆�ł̕������ł̃}�l�W�����g��ΊO�I�ȏ�M���ɂ����������Ƃ��ł��A�d���̎�����L���邱�Ƃɖ𗧂����ƍl����B �@����́AFM �̎��i�擾�œ����m������ɁA���܂��܂ȓs�s�J���Ɩ��Ɏ��g�݁A�u�n�}�Ɏc��d���v��̌����Ă��������ƍl���Ă���B�����Â���Ɋւ��邠����t�F�[�Y�ɂ����āA�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�̃m�E�n�E�����������Ƃ��ł���A���܂��܂ȃX�e�[�N�z���_�[�Ƃ̐M���W���\�z�ł��A���̌��ʂƂ��ė��p���₷��������錚���Â���Ɋ�^����ƍl����B���Ɍ�������K�͂ɂȂ�̂Ɣ�Ⴕ�āA�����S�̂̂��Ƃ��l���鎋��̍L�������߂��A�ӔC���傫���Ȃ�B�����I�ɂ́A�t�@�V���e�B�}�l�W�����g��ʂ��āA�����錚���̖��͂≿�l�����߂���悤�Ȑl�ނɂȂ邱�Ƃ�ڎw���Ă��������B�܂��A�����S�����������̊Ǘ��E�^�p�Ɩ��ɏ]�����钆�ŁAFM �̖{���̈Ӗ��ł���u�t�@�V���e�B��ʂ����o�c�����v�����H���Ă��������B |
����܂łɌf�ڂ����t�@�V���e�B�}�l�W���[�̐�

�� FM�̒m���Ŏ�����������v�̃t���A�����Ɖ^�c���v
�@�J �G�G�i����������v�j

�@�����v�ł́A���z��s�s�v��̐v�Ɩ��ɉ����A�v���W�F�N�g�}�l�W�����g�iPM�j�A�f�U�C���R���T���e�B���O�A�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�iFM�j�A�R�[�|���[�g���A���G�X�e�[�g�iCRE�j�ɂ��ϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B���͌��z�ӏ����U���Ă��܂������A���Ќ��FM��PM�A����ɂ͌����̓����^�p��Ǘ��^�c�Ƃ���������ɂ��g��邱�ƂƂȂ�A�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎��i���擾���܂����B���i�擾��ʂ��āA�{�ݓ����]����@�ȂǁA�w������ɂ͐G���@��̂Ȃ������m�����w�сA���z������ɂ킽��L�͂ȕ���ł��邱�Ƃ��������܂����B
�@���Ђł́A�I�t�B�X��Ԃ̊��p���d�v�ȃg�s�b�N�̈�ƂȂ��Ă���A��N�ɂ͑��I�t�B�X���C�v���W�F�N�g����18����{FM��܂���܂��A�����{�Ђɂ͋��n��ԁuPYNT�v���a�����܂����B�������A�O���[�v��Ђ̓����ɔ����t���A������E�������ւ̑Ή��A�G���A���Ƃɂ���̂���I�t�B�X���̉��P���ً}�ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�@���͓����n��ŁAFM��PM�A�I�[�i�[�Y�R���T���e�B���O�̎��_����A���i�擾���Ɋw�����K�C�h�w�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�x�Ɋ�Â��A�Г��̌o�c�헪���̃��[�N�v���C�X��{���j�̍����⏕���܂����B�܂��AFM�̒��������s�v���Ă�v�������̐����A�v���W�F�N�g�̐i�s�Ǘ��A�]���A���P�̃v���Z�X���S�����A��i���A�ѓc���A�|���ɕ��U����I�t�B�X�t���A�̓����Ɣz�u�����肷�郍�[�����O�v���X�^�b�L���O�̌������s���܂����B
�@���[�N�v���C�X��{���j�̍���ɍۂ��ẮA�u���n�̏�v�u�����₷�����v�u�J�[�{���j���[�g�����v�u�I�t�B�X�^�p�V�X�e���v�Ȃǂ̍��ڂ��ƂɃr�W��������������A�e�I�t�B�X�̌X�̗^�����i1�l������̎����ʐρA�L���r�l�b�g���A�t���[�A�h���X�ȁA�ȃG�l�ڕW�l�A��c�\��V�X�e���Ȃǁj��ݒ肵�܂����B
�@�܂��AFM�̒��������s�v���[�����O�ƃX�^�b�L���O�̊�{�v��ł́A�Ј��pWi-Fi�ɐڑ�����Ă���[��������Ƀt���A���Ƃ̍��G�x���v�����A�����Ƀt���A�v������]�����ĉ��P���ׂ��G���A����肵�܂����B����ɁA����̐E�����������z���āA���K�ȃI�t�B�X�����ێ����邽�߂ɁA���e�\�l������^�C�~���O��\�����A���������s�v��̒�Ă��s���܂����B�X�^�b�L���O�̍ۂɂ́A�f�U�C����c�ɕK�v�ȑ傫�ȉ�c�e�[�u����A�l��ƂɓK���������Ȃ̊m�ۂȂǁA���傲�Ƃ̓��L�̃j�[�Y���l�����A�Ј��̃��[�N�p�t�H�[�}���X����Ɋ�^����z�u���������܂����B
�@�I�t�B�X���C�v���W�F�N�g�̐i�s�Ǘ��ł́A�������ꂽ����̃t���A���C�⎷���ȑ����̂��߂̃��C�A�E�g�ύX�A�Г��։����ɔ������i�����̐}�����C�u�����[�ւ̉��C���S�����܂����B
�@���Ђ�FM��PM�A�v�A�C���e���A��������Г��ɗi���A�H���ȊO�͂قڃC���n�E�X�Ń����o�[�B���Ă��܂��B���̂��߁A�Ɩ���̗����Г��̘A���E���F�̐������G�����A��J������܂����B�������A���Ђ̃I�t�B�X��ΏۂƂ���FM����Ɋւ�邱�ƂŁA�t�@�V���e�B�̌������C��̌��ʂŊ�����邱�Ƃ��ł��A��ϊw�т̑����v���W�F�N�g�ƂȂ�܂����B
�@���Ђł́A�I�t�B�X��Ԃ̊��p���d�v�ȃg�s�b�N�̈�ƂȂ��Ă���A��N�ɂ͑��I�t�B�X���C�v���W�F�N�g����18����{FM��܂���܂��A�����{�Ђɂ͋��n��ԁuPYNT�v���a�����܂����B�������A�O���[�v��Ђ̓����ɔ����t���A������E�������ւ̑Ή��A�G���A���Ƃɂ���̂���I�t�B�X���̉��P���ً}�ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�@���͓����n��ŁAFM��PM�A�I�[�i�[�Y�R���T���e�B���O�̎��_����A���i�擾���Ɋw�����K�C�h�w�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�x�Ɋ�Â��A�Г��̌o�c�헪���̃��[�N�v���C�X��{���j�̍����⏕���܂����B�܂��AFM�̒��������s�v���Ă�v�������̐����A�v���W�F�N�g�̐i�s�Ǘ��A�]���A���P�̃v���Z�X���S�����A��i���A�ѓc���A�|���ɕ��U����I�t�B�X�t���A�̓����Ɣz�u�����肷�郍�[�����O�v���X�^�b�L���O�̌������s���܂����B
�@���[�N�v���C�X��{���j�̍���ɍۂ��ẮA�u���n�̏�v�u�����₷�����v�u�J�[�{���j���[�g�����v�u�I�t�B�X�^�p�V�X�e���v�Ȃǂ̍��ڂ��ƂɃr�W��������������A�e�I�t�B�X�̌X�̗^�����i1�l������̎����ʐρA�L���r�l�b�g���A�t���[�A�h���X�ȁA�ȃG�l�ڕW�l�A��c�\��V�X�e���Ȃǁj��ݒ肵�܂����B
�@�܂��AFM�̒��������s�v���[�����O�ƃX�^�b�L���O�̊�{�v��ł́A�Ј��pWi-Fi�ɐڑ�����Ă���[��������Ƀt���A���Ƃ̍��G�x���v�����A�����Ƀt���A�v������]�����ĉ��P���ׂ��G���A����肵�܂����B����ɁA����̐E�����������z���āA���K�ȃI�t�B�X�����ێ����邽�߂ɁA���e�\�l������^�C�~���O��\�����A���������s�v��̒�Ă��s���܂����B�X�^�b�L���O�̍ۂɂ́A�f�U�C����c�ɕK�v�ȑ傫�ȉ�c�e�[�u����A�l��ƂɓK���������Ȃ̊m�ۂȂǁA���傲�Ƃ̓��L�̃j�[�Y���l�����A�Ј��̃��[�N�p�t�H�[�}���X����Ɋ�^����z�u���������܂����B
�@�I�t�B�X���C�v���W�F�N�g�̐i�s�Ǘ��ł́A�������ꂽ����̃t���A���C�⎷���ȑ����̂��߂̃��C�A�E�g�ύX�A�Г��։����ɔ������i�����̐}�����C�u�����[�ւ̉��C���S�����܂����B
�@���Ђ�FM��PM�A�v�A�C���e���A��������Г��ɗi���A�H���ȊO�͂قڃC���n�E�X�Ń����o�[�B���Ă��܂��B���̂��߁A�Ɩ���̗����Г��̘A���E���F�̐������G�����A��J������܂����B�������A���Ђ̃I�t�B�X��ΏۂƂ���FM����Ɋւ�邱�ƂŁA�t�@�V���e�B�̌������C��̌��ʂŊ�����邱�Ƃ��ł��A��ϊw�т̑����v���W�F�N�g�ƂȂ�܂����B

�� �s�����E���t�@�V���e�B�}�l�W���[�Ƃ��Ă̎��H
�@�_�� ����i�s���s�����s�s���j

�@���́A1999�N���猚�z�Z�p�E���Ƃ��Ďs���s�����ɋΖ�����26�N�ځB����܂łɓs�s�v��A���z�w���A���S�s�X�n�������A���z�c�U�A�s���ɐ����E�Ǘ����̋Ɩ����o�āA���݂͌��z�w������Ŗ��ԏZ��̑ϐk�����i�Ɩ��Ɍg����Ă��܂��B
�@���̃t�@�V���e�B�}�l�W�����g�iFM�j�Ƃ̏o��́A2010�N�A���z�c�U����ɔz�����ꂽ���ɑk��܂��B�����A�������̂̐�i�I��FM�̎��g�݂����@���ďՌ�������i����A�u�����{�݂̐����ƕۑS����̓I�ɑ����A�{�݊Ǘ�����ɉ������h���Ďs�S�̂Ƃ��čœK����}��FM�́A�����ɕK�v�ƂȂ�̂Ō������Ȃ����v�Ǝw���������Ƃ��@��FM�̕����J�n�B������ߒ��ŔF��t�@�V���e�B�}�l�W���[���i��m��A2011�N�Ɏ��A���i���擾���܂����B
�@���i�擾��AFM�̒m���⎑�i�����H�I�Ɏ����Ɋ��������̂́A2017�N�x����2022�N�x�܂Ŕz������Ă�����������Ōg������s���ɐ����E�Ǘ��Ɩ��ł��B
�@�s���s�̎s���ɂ̂����A���ɂƂ��Ă̒��S�I�ȋ@�\��S���{���ɂ́A1972�N�z�őϐk���\�̕s���ƘV���������ƂȂ��Ă������Ƃ���A2011�N�̓����{��k�Ђ��@�ɖh�Ћ��_�@�\�̂ł��邾�������̋����E�m�ۂɌ����ϐk��������A�i�ق̑�Ƃ��čЊQ�Ή��@�\�𒆐S�ɖ{���ɂ̖��̋@�\��S���Ɛk�\���̖h�В��Ɂi����P���Ɂj���s�����~�n���ɐV�z���A�����̖{���ɂ͍��w�K��s�g�p�ɂ��Ē�w�K�Ɍ����2���ɂƂ��ē��ʂ̊Ԏg�p�p�����邱�ƂƂȂ�܂����B
�@������������ɔz���ɂȂ���2017�N�x�́A��1���ɂ̐����̍ŏI�N�x�ł���A���̍ŏ��̎d���́A��1���ɐ����̎d�グ�Ƌ��p�J�n�Ɍ������ړ]�i���z�j�ł����B���ɑ��p�I�ɕi�����\���������Ă̔��i������A���j�o�[�T���f�U�C�����ӎ������ē��T�C���̐����A���z�Ǝ҂̃m�E�n�E���ő���������O�A�x3���Ԃň�C�ɍs�����ړ]�i���z�j�ɂ��ẮA�܂���FM�̎��H�ł����B
�@���̌�A2018�N�x�ɂ͑�2���ɂ̋@�\���w�K�ɏW����ړ]�i���z�j���s���ƂƂ��ɁA��2���ɂ́u���ʂ̗��p�v��̔��{�I�ȑϐk��i���ɋ��x����j�̌������X�^�[�g���܂����B
�@���ɋ��x����ɂ��ẮA�܂�2018�N�x����2�J�N�ő�2���ɂ̔��{�I�ȑϐk����u�ϐk���C�v�Ɓu���ւ��v�̂ǂ���̕������Ői�߂邩�̌������s���A�C�j�V�����R�X�g�ƒ����I�ȃ����j���O�R�X�g�܂����g�[�^���R�X�g�⒡�ɂƂ��Ă̎g��������r���������ʁA�u���ւ��v�̕������Ői�߂邱�ƂƂȂ�܂����B
�@������2020�N�x����2�J�N�ő�2���ɂ̌��ւ��ƂȂ�V���ɐ����̊�{�v��̍���A2021�N����2�J�N�Ŋ�{�v���s�����Ƃ���ł��B
�@����璡�ɋ��x����̌����́A�ϑ��Ɩ��Ƃ��Ė��Ԋ�Ƃ̎x���čs���܂������A�ϑ��d�l�ɂ����ċƖ��̐��ɔF��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎Q������߁A�ϑ���̖��ԃt�@�V���e�B�}�l�W���[�Ƃ̑Θb�ɂ��AFM�ʂ���̓��e��[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B���Ɋ�{�v��ɂ��ẮA�������Ԃ��V�^�R���i�E�C���X�̖������������Əd�Ȃ������Ƃ���A�A�t�^�[�R���i�̐V���ȓ������ɑΉ��������[�N�v���C�X�Â���Ƃ��ĐV���Ȓm���荞�ނ��Ƃ��ł��܂����B
�@�܂��O�i�܂ł̃v���W�F�N�g�Ǘ��I�Ȓ��ɐ����̋Ɩ��ƕ��s���āA���ɂ̉^�c�ێ��ɂ��g����Ă��܂������A���ɘV�����ɂ���肪���݉����Ă����2���ɂ̈ێ��Ǘ��ɂ��ẮA�ݔ����̓˔��I�ȕs���䕗���̍ЊQ�ł̊e���j���Ƃ̐킢�ł����B�ȑO����ێ��Ǘ��̂��߂̊�{�I��PDCA�T�C�N���͂�����x�m������Ă��܂������A���ɂł̋Ɩ��p�������炷�ׂ�OODA���[�v�ɂ��Ջ@���ςȉۑ�Ή������߂��邱�Ƃ����풃�ю��ŁA�^�c�ێ��ɂ��Ă͖{���ɒb����ꂽ�ȂƎ������Ă��܂��B
�@�ȏ�Љ�Ă������g�݂͌����������̉��ŋꂵ�����Ƃ������������̂́A��ɖ��������đO�����ɖ��邭�y�����Ղ�ł��܂����B�s�����ɂ͂��̑��ɂ����l��FM�̋Ɩ�������܂��B������z������镔��ɂ��FM�̒m�����������Ɩ��͕ς���Ă��܂����A����Ƀ|�W�e�B�u�Ɋw�тȂ�����g��ł��������Ǝv���܂��B
�@���̃t�@�V���e�B�}�l�W�����g�iFM�j�Ƃ̏o��́A2010�N�A���z�c�U����ɔz�����ꂽ���ɑk��܂��B�����A�������̂̐�i�I��FM�̎��g�݂����@���ďՌ�������i����A�u�����{�݂̐����ƕۑS����̓I�ɑ����A�{�݊Ǘ�����ɉ������h���Ďs�S�̂Ƃ��čœK����}��FM�́A�����ɕK�v�ƂȂ�̂Ō������Ȃ����v�Ǝw���������Ƃ��@��FM�̕����J�n�B������ߒ��ŔF��t�@�V���e�B�}�l�W���[���i��m��A2011�N�Ɏ��A���i���擾���܂����B
�@���i�擾��AFM�̒m���⎑�i�����H�I�Ɏ����Ɋ��������̂́A2017�N�x����2022�N�x�܂Ŕz������Ă�����������Ōg������s���ɐ����E�Ǘ��Ɩ��ł��B
�@�s���s�̎s���ɂ̂����A���ɂƂ��Ă̒��S�I�ȋ@�\��S���{���ɂ́A1972�N�z�őϐk���\�̕s���ƘV���������ƂȂ��Ă������Ƃ���A2011�N�̓����{��k�Ђ��@�ɖh�Ћ��_�@�\�̂ł��邾�������̋����E�m�ۂɌ����ϐk��������A�i�ق̑�Ƃ��čЊQ�Ή��@�\�𒆐S�ɖ{���ɂ̖��̋@�\��S���Ɛk�\���̖h�В��Ɂi����P���Ɂj���s�����~�n���ɐV�z���A�����̖{���ɂ͍��w�K��s�g�p�ɂ��Ē�w�K�Ɍ����2���ɂƂ��ē��ʂ̊Ԏg�p�p�����邱�ƂƂȂ�܂����B
�@������������ɔz���ɂȂ���2017�N�x�́A��1���ɂ̐����̍ŏI�N�x�ł���A���̍ŏ��̎d���́A��1���ɐ����̎d�グ�Ƌ��p�J�n�Ɍ������ړ]�i���z�j�ł����B���ɑ��p�I�ɕi�����\���������Ă̔��i������A���j�o�[�T���f�U�C�����ӎ������ē��T�C���̐����A���z�Ǝ҂̃m�E�n�E���ő���������O�A�x3���Ԃň�C�ɍs�����ړ]�i���z�j�ɂ��ẮA�܂���FM�̎��H�ł����B
�@���̌�A2018�N�x�ɂ͑�2���ɂ̋@�\���w�K�ɏW����ړ]�i���z�j���s���ƂƂ��ɁA��2���ɂ́u���ʂ̗��p�v��̔��{�I�ȑϐk��i���ɋ��x����j�̌������X�^�[�g���܂����B
�@���ɋ��x����ɂ��ẮA�܂�2018�N�x����2�J�N�ő�2���ɂ̔��{�I�ȑϐk����u�ϐk���C�v�Ɓu���ւ��v�̂ǂ���̕������Ői�߂邩�̌������s���A�C�j�V�����R�X�g�ƒ����I�ȃ����j���O�R�X�g�܂����g�[�^���R�X�g�⒡�ɂƂ��Ă̎g��������r���������ʁA�u���ւ��v�̕������Ői�߂邱�ƂƂȂ�܂����B
�@������2020�N�x����2�J�N�ő�2���ɂ̌��ւ��ƂȂ�V���ɐ����̊�{�v��̍���A2021�N����2�J�N�Ŋ�{�v���s�����Ƃ���ł��B
�@����璡�ɋ��x����̌����́A�ϑ��Ɩ��Ƃ��Ė��Ԋ�Ƃ̎x���čs���܂������A�ϑ��d�l�ɂ����ċƖ��̐��ɔF��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎Q������߁A�ϑ���̖��ԃt�@�V���e�B�}�l�W���[�Ƃ̑Θb�ɂ��AFM�ʂ���̓��e��[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B���Ɋ�{�v��ɂ��ẮA�������Ԃ��V�^�R���i�E�C���X�̖������������Əd�Ȃ������Ƃ���A�A�t�^�[�R���i�̐V���ȓ������ɑΉ��������[�N�v���C�X�Â���Ƃ��ĐV���Ȓm���荞�ނ��Ƃ��ł��܂����B
�@�܂��O�i�܂ł̃v���W�F�N�g�Ǘ��I�Ȓ��ɐ����̋Ɩ��ƕ��s���āA���ɂ̉^�c�ێ��ɂ��g����Ă��܂������A���ɘV�����ɂ���肪���݉����Ă����2���ɂ̈ێ��Ǘ��ɂ��ẮA�ݔ����̓˔��I�ȕs���䕗���̍ЊQ�ł̊e���j���Ƃ̐킢�ł����B�ȑO����ێ��Ǘ��̂��߂̊�{�I��PDCA�T�C�N���͂�����x�m������Ă��܂������A���ɂł̋Ɩ��p�������炷�ׂ�OODA���[�v�ɂ��Ջ@���ςȉۑ�Ή������߂��邱�Ƃ����풃�ю��ŁA�^�c�ێ��ɂ��Ă͖{���ɒb����ꂽ�ȂƎ������Ă��܂��B
�@�ȏ�Љ�Ă������g�݂͌����������̉��ŋꂵ�����Ƃ������������̂́A��ɖ��������đO�����ɖ��邭�y�����Ղ�ł��܂����B�s�����ɂ͂��̑��ɂ����l��FM�̋Ɩ�������܂��B������z������镔��ɂ��FM�̒m�����������Ɩ��͕ς���Ă��܂����A����Ƀ|�W�e�B�u�Ɋw�тȂ�����g��ł��������Ǝv���܂��B
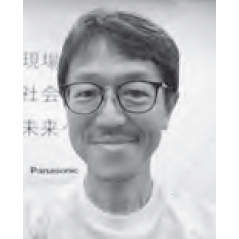
�� ���������Ȃ��Ђ�����
�@�F�J ���V�i�p�i�\�j�b�N�R�l�N�g������Ёj
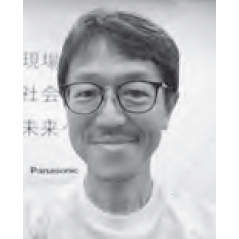
�@�p�i�\�j�b�N�R�l�N�g��BtoB �̂��q�l�Ɍ����āA���q�l�̃r�W�l�X�̌���Ƀ\�����[�V�����ōv������p�i�\�j�b�N�O���[�v�̎��Ɖ�Ђł��B
�@���Ђ�2017 �N�ɎЊO���璅�C�����o�c�ҁA����s�̃��[�h�Ŋ�Ɖ��v�Ɏ��g�݁A�����Ƃ��ăJ���`���[���v���d�����đ�K�͂ȃI�t�B�X���v���s���܂����B
�@�������͌o�c���̗���Ńv���W�F�N�g�ɎQ�悵�A�{�Е�����ォ�瓌���ֈړ]�A���^�I�t�B�X���t���[�A�h���X�Ɉ�V�A��������p�~���ĎВ����I�[�v���X�y�[�X�ɏo�Ă��Ă��炢�܂����B��Ӊ��B����߃I�[�v���ŃX�s�[�f�B�A�t�F�A�ȃJ���`���[��ڎw�����̂ł��B
�@�E�����^�p��ς��邾���ŁA��Ђ��傫���ς��A�������g����Ђ��y�����Ȃ�܂����B�t�@�V���e�B�̗͂���������M�d�Ȍ��̌��������Ǝv���܂��B���̎��g�݂Ńp�i�\�j�b�N�O���[�v�Ƃ���2018 �NJFMA����܂������������Ƃ��ł��܂����B
�@���̌�A���͉������ăI�t�B�X���v�̎劲�����������������Ɉٓ��ɂȂ�܂����B�{�ЁE�J�����_�E�H��ȂǓ��{�̎�v9 ���_�ȂǍ������Ə�̉^�c���s���������A���̋Ɩ����v�S���Ƃ��č�����3 �N�O�ɒ��C���܂����B
�@�����͏��߂Ă̌o���Œm��Ȃ��Ɩ�����A�܂��ȑO�͋��_���Ƃɕʉ�Ђ������o�܂������ē����Ɩ��ł����_���Ƃɂ������o���o���̌ʍœK�̉^�c�ŁA�Ɩ��̑S�̑��������Ȃ���Ԃł����B�ǂ�����������������̂��r���ɕ��Ă���܂����B
�@���s����𑱂��钆�A�R���T���^���g�̃N���C�O�J�b�N�X������JFMA ��F��t�@�V���e�B�}�l�W���[���Љ��A�w�����K�C�h �t�@�V���e�B�}�l�W�����g�x����ɂ��܂����B�ǂݎn�߂�Ƒ��͂�������̘A���ł����B
�@�{�݂�E����̉��l�����߂āA���Ƃ̐�����]�ƈ��̐����E�G���Q�[�W�����g�̌���ɂȂ����邱�ƁA�헪�I��PDCA �T�C�N�����܂킵�Ĕ�p�̌������p���邱�Ƃő傫���o�c�v�����ł��邱�ƂȂǁAFM �̊T�O�Ƃ��̏d�v���E�|�e���V�������悭�����ł��܂����B�ƊE�̒n�}�◅�j�Ղ���ɓ��ꂽ�悤�Ȋ��o�ŁA�Y��ł��������������o���āA�傢�Ƀ��`�x�[�V���������܂����̂��o���Ă��܂��B���ɉ��v��S�����铯���Ɨ�܂������Ȃ���w�K�𑱂��A���i���擾�ł��܂����B
�@���̌��FM �̒m���āA���_�o���o���̌ʍœK��S�̍œK�����Č��������v�Ɏ��g��ł��܂��B
�@�{�݊Ǘ��A���[�N�v���C�X�ȂNj@�\�i�t�@���N�V�����j���ƂɁA���{�S���_�̉������h�����v���W�F�N�g�`�[���u�t�@���N�V�����`�[���v���B���_�����o�[�̋��͂Ȃ���e�t�@���N�V�����̂���ׂ��p���c�_���āA�^�c��̍���A�Ɩ��v���Z�X�̕W������i�߁A�Ɩ��W��ɂ������^�c��ڎw���Ċ����𑱂��Ă��܂��B
�@�\�Z�̊Ǘ������_���ƂɃo���o���ł������A�����K�C�h�̃t�@�V���e�B�R�X�g�Ǘ��̌n�ɂ̂��Ƃ��Ĕ�p�Ǘ����ł���悤�Ɏd�g�݂𐮂��Ă����܂����B
�@������FM ����Ƃ���PDCA ���܂킹��̐����m�������āA���_�ʉ^�c����t�@���N�V�����ʂ̑g�D�^�c�ւ̐�ւ���ژ_��ł��܂��B
�@�܂�JFMA �̃Z�~�i�[�ɂ������ւ��b�ɂȂ�܂����B��N11 ���̏���FM �X�N�[���֕����ŎQ������ƁA4 ���̓�\��������������Ď�u�AFM �̗�����[�߂Ă���܂����B�������̔F��t�@�V���e�B�}�l�W���[�͌���5 ���A���N���������킵�Ă��܂��BFM �̃t���[�����[�N�𗝉������H�ł���l�𑝂₵�ċ����g�D�ɂ��Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�@2 �N�O�ɑ������ł́u���������Ȃ��Ђ�����v�Ƃ����~�b�V������S���Ō��߂܂����BFM �͉�Ђ̊��C�ݏo���A�]�ƈ����K���ɂł���ƂĂ��d�v�ł�肪���̂���d���ł��B�ƊE�̒m������������FM��i�������Ă������ƂŁA�~�b�V���������������Ă��������Ǝv���܂��B
�@���Ђ�2017 �N�ɎЊO���璅�C�����o�c�ҁA����s�̃��[�h�Ŋ�Ɖ��v�Ɏ��g�݁A�����Ƃ��ăJ���`���[���v���d�����đ�K�͂ȃI�t�B�X���v���s���܂����B
�@�������͌o�c���̗���Ńv���W�F�N�g�ɎQ�悵�A�{�Е�����ォ�瓌���ֈړ]�A���^�I�t�B�X���t���[�A�h���X�Ɉ�V�A��������p�~���ĎВ����I�[�v���X�y�[�X�ɏo�Ă��Ă��炢�܂����B��Ӊ��B����߃I�[�v���ŃX�s�[�f�B�A�t�F�A�ȃJ���`���[��ڎw�����̂ł��B
�@�E�����^�p��ς��邾���ŁA��Ђ��傫���ς��A�������g����Ђ��y�����Ȃ�܂����B�t�@�V���e�B�̗͂���������M�d�Ȍ��̌��������Ǝv���܂��B���̎��g�݂Ńp�i�\�j�b�N�O���[�v�Ƃ���2018 �NJFMA����܂������������Ƃ��ł��܂����B
�@���̌�A���͉������ăI�t�B�X���v�̎劲�����������������Ɉٓ��ɂȂ�܂����B�{�ЁE�J�����_�E�H��ȂǓ��{�̎�v9 ���_�ȂǍ������Ə�̉^�c���s���������A���̋Ɩ����v�S���Ƃ��č�����3 �N�O�ɒ��C���܂����B
�@�����͏��߂Ă̌o���Œm��Ȃ��Ɩ�����A�܂��ȑO�͋��_���Ƃɕʉ�Ђ������o�܂������ē����Ɩ��ł����_���Ƃɂ������o���o���̌ʍœK�̉^�c�ŁA�Ɩ��̑S�̑��������Ȃ���Ԃł����B�ǂ�����������������̂��r���ɕ��Ă���܂����B
�@���s����𑱂��钆�A�R���T���^���g�̃N���C�O�J�b�N�X������JFMA ��F��t�@�V���e�B�}�l�W���[���Љ��A�w�����K�C�h �t�@�V���e�B�}�l�W�����g�x����ɂ��܂����B�ǂݎn�߂�Ƒ��͂�������̘A���ł����B
�@�{�݂�E����̉��l�����߂āA���Ƃ̐�����]�ƈ��̐����E�G���Q�[�W�����g�̌���ɂȂ����邱�ƁA�헪�I��PDCA �T�C�N�����܂킵�Ĕ�p�̌������p���邱�Ƃő傫���o�c�v�����ł��邱�ƂȂǁAFM �̊T�O�Ƃ��̏d�v���E�|�e���V�������悭�����ł��܂����B�ƊE�̒n�}�◅�j�Ղ���ɓ��ꂽ�悤�Ȋ��o�ŁA�Y��ł��������������o���āA�傢�Ƀ��`�x�[�V���������܂����̂��o���Ă��܂��B���ɉ��v��S�����铯���Ɨ�܂������Ȃ���w�K�𑱂��A���i���擾�ł��܂����B
�@���̌��FM �̒m���āA���_�o���o���̌ʍœK��S�̍œK�����Č��������v�Ɏ��g��ł��܂��B
�@�{�݊Ǘ��A���[�N�v���C�X�ȂNj@�\�i�t�@���N�V�����j���ƂɁA���{�S���_�̉������h�����v���W�F�N�g�`�[���u�t�@���N�V�����`�[���v���B���_�����o�[�̋��͂Ȃ���e�t�@���N�V�����̂���ׂ��p���c�_���āA�^�c��̍���A�Ɩ��v���Z�X�̕W������i�߁A�Ɩ��W��ɂ������^�c��ڎw���Ċ����𑱂��Ă��܂��B
�@�\�Z�̊Ǘ������_���ƂɃo���o���ł������A�����K�C�h�̃t�@�V���e�B�R�X�g�Ǘ��̌n�ɂ̂��Ƃ��Ĕ�p�Ǘ����ł���悤�Ɏd�g�݂𐮂��Ă����܂����B
�@������FM ����Ƃ���PDCA ���܂킹��̐����m�������āA���_�ʉ^�c����t�@���N�V�����ʂ̑g�D�^�c�ւ̐�ւ���ژ_��ł��܂��B
�@�܂�JFMA �̃Z�~�i�[�ɂ������ւ��b�ɂȂ�܂����B��N11 ���̏���FM �X�N�[���֕����ŎQ������ƁA4 ���̓�\��������������Ď�u�AFM �̗�����[�߂Ă���܂����B�������̔F��t�@�V���e�B�}�l�W���[�͌���5 ���A���N���������킵�Ă��܂��BFM �̃t���[�����[�N�𗝉������H�ł���l�𑝂₵�ċ����g�D�ɂ��Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�@2 �N�O�ɑ������ł́u���������Ȃ��Ђ�����v�Ƃ����~�b�V������S���Ō��߂܂����BFM �͉�Ђ̊��C�ݏo���A�]�ƈ����K���ɂł���ƂĂ��d�v�ł�肪���̂���d���ł��B�ƊE�̒m������������FM��i�������Ă������ƂŁA�~�b�V���������������Ă��������Ǝv���܂��B
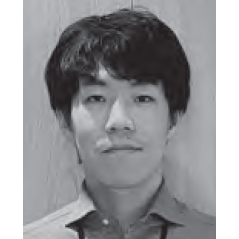
�� �T�X�e�i�u���ȎЉ�̎����Ɋ�^�ł���
�@�@�t�@�V���e�B�}�l�W���[���߂�����
�@�J �G�G�i����������v�j
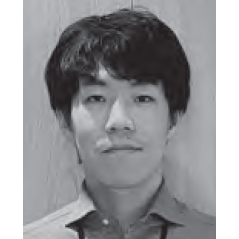
���Ђ���̌o��
�@�������Ђɓ��Ђ������R�́A�Ж��̒ʂ�A�����̍\�z����ێ��܂Ńt�@�V���e�B�ɕ��L���ւ�闧��A������t�@�V���e�B�}�l�W���[�ɂȂ肽���Ǝv��������ł���B
�@���ۂɁA���Г����͌��z�R�X�g�v��E�ώZ��H���ė����s�������ɏ������A�O���[�v��Ђۗ̕L���鑽���{�݂̉��C�H�������{����Ɩ��ɏ]�������B���̌�A��Ɍ����̈ێ��ۑS��S�����݂̕����Ɉٓ����A�_���E�ێ�̓����Ǘ��Ɩ��₨�q�l�ւ̕ۑS��ċƖ���S�����Ă���B
�@���̂悤�Ɂu�����̍\�z����ێ��܂Ńt�@�V���e�B�ɕ��L���ւ��v�Ƃ������̓��З��R�ɑ������o�������ł���A�t�@�V���e�B�}�l�W���[�Ƃ��Ă̊�{�I�Ȓm�����܂��͎擾�������Ǝv���Ă������߁A�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[���i�����Ў����玎���������擾�ł����B
�ێ��ۑS�̗���ł̃t�@�V���e�B�}�l�W�����g
�@���݂̈ێ��ۑS�̕����ɂ����āA�Ǘ����邨�q�l�ۗ̕L�{�݂̓o�u�����Ɍ��݂��ꂽ�I�t�B�X�p�r�̌����������A����I�ȓ_���E�ێ���{���Ȃ��猚�����p�҂̎��ƌp�����̊m�ۂƌ����̒��������ɓw�߁A�o�N�ɂ��ɑ��Ă͗\�h�ۑS�I�ϓ_���璆�����C�U�v��𗧈Ă��I�[�i�[�l�֒�Ă��邱�ƂŃ��C�t�T�C�N���R�X�g�̒ጸ�Ɋ�^���Ă���B
�@�ȑO�̕����ł͎�Ɍ�����̂̉��C�H�����s���Ɩ��ɏ]�����Ă������A���݂̕����ł͌����ݔ��Ǘ�����ɒS���Ă���B����܂ŐG��邱�Ƃ̏��Ȃ����������ݔ��m�����K�v�Ƃ�����ʂ������A���X�ƕς�錚���ݔ��ɃL���b�`�A�b�v�ł���悤�ɁA���ۂɌ���֓_�����s�Ȃǂ��Ȃ�����X���r���Ă���Œ��ł���B
�@�܂��A�������C�U�v��̗��Ăɂ����ẮA�����ݔ��Ǘ��ł̓���I�ȓ_���E�ێ猋�ʂ�g���u���E�̏ᗚ�������Ƃɐݔ��������A�v���p�e�B�}�l�W���[�Ɨ\�Z���܂߂����c�����{���Ȃ���A5 �N�Ȃ���10 �N�̗\�h�ۑS�I�ȏC�U�v����I�[�i�[�l�֒�Ă���B���i�����Ŋw�v��I�ۑS�̍l������ۑS���ڂ̏d�v�x���ނ̍l�����́A�v�旧�Ẵv���Z�X�̒��Ŋ������Ă���Ɗ����Ă���B
�n�[�h�ʂɂƂǂ܂�Ȃ��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎d��
�@��L�̂悤�Ȉێ��ۑS�i���Ђł͌����ێ��Ǘ��Ɩ��t���Ă���j�Ɩ����}�l�W�����g���Ă��������ŁA�N�X�[�������Ă���Ɩ��]���҂̍���E�l�ޕs���̉ۑ�ɂ��Ή����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A���̐l�ވ琬���x�̊�旧�āA�c�[����p�����ێ��Ǘ���DX���A���Ђ����i���Ă���IWMS�iIntegrated WorkplaceManagement System�j�ɂ��u�G���A����^�ێ�T�[�r�X�v�̓������i�ȂǁA���܂��܂Ȋϓ_����{���ł��o���Ȃ���ۑ�ɑΉ����Ă���B�����������q���[�}�����\�[�X�̉ۑ�ւ̑Ή���AICT �����p���Čo�c�ۑ����������Ɩ����A�o�c���l������x�����m���n���Ɛ��Y��������x������FM �̒S�������̈�ł���Ƒ����Ȃ�����X�]�����Ă���B
����̓W�]
�@�ȑO�A�t�@�V���e�B�}�l�W���[�������i�҂̐��Ƃ��Ċ�e�����Ă����������ۂɁA�u��Ƃ�FM �헪�E�v��̗��Ă⒆�����v��̎��s�Ɍg��邱�Ƃ̂ł���t�@�V���e�B�}�l�W���[���߂��������v�ƋL�ڂ����悤�ɁA�ڕW�Ƃ��铹�𒅎��ɐi��ł���Ǝ������Ă���B���l�ς̑��l���ł�萳���̂Ȃ�����ւƐi��ł��钆�ŁAFM �̗̈�͂���Ɋg�債�Ă������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ����A���̕ω��Ƀt�@�V���e�B�}�l�W���[���Ջ@���ςɑΉ��ł���悤�ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƍl���Ă���B�l�I�ɂ��A�v�E�H���ė���ێ��Ǘ��ɂƂǂ܂炸�s���Y��[�N�v���C�X�\�z�A�Ђ��Ă͌o�c�A�����A�l���AICT �Ƒ��l�ȕ�����o�����A�ω��̌������Љ�̒��ł����L���m���������Ď����\�Љ��z�^�Љ�̎����Ɋ�^�ł���t�@�V���e�B�}�l�W���[�Ƃ��Ċ��Ă��������B
�@�������Ђɓ��Ђ������R�́A�Ж��̒ʂ�A�����̍\�z����ێ��܂Ńt�@�V���e�B�ɕ��L���ւ�闧��A������t�@�V���e�B�}�l�W���[�ɂȂ肽���Ǝv��������ł���B
�@���ۂɁA���Г����͌��z�R�X�g�v��E�ώZ��H���ė����s�������ɏ������A�O���[�v��Ђۗ̕L���鑽���{�݂̉��C�H�������{����Ɩ��ɏ]�������B���̌�A��Ɍ����̈ێ��ۑS��S�����݂̕����Ɉٓ����A�_���E�ێ�̓����Ǘ��Ɩ��₨�q�l�ւ̕ۑS��ċƖ���S�����Ă���B
�@���̂悤�Ɂu�����̍\�z����ێ��܂Ńt�@�V���e�B�ɕ��L���ւ��v�Ƃ������̓��З��R�ɑ������o�������ł���A�t�@�V���e�B�}�l�W���[�Ƃ��Ă̊�{�I�Ȓm�����܂��͎擾�������Ǝv���Ă������߁A�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[���i�����Ў����玎���������擾�ł����B
�ێ��ۑS�̗���ł̃t�@�V���e�B�}�l�W�����g
�@���݂̈ێ��ۑS�̕����ɂ����āA�Ǘ����邨�q�l�ۗ̕L�{�݂̓o�u�����Ɍ��݂��ꂽ�I�t�B�X�p�r�̌����������A����I�ȓ_���E�ێ���{���Ȃ��猚�����p�҂̎��ƌp�����̊m�ۂƌ����̒��������ɓw�߁A�o�N�ɂ��ɑ��Ă͗\�h�ۑS�I�ϓ_���璆�����C�U�v��𗧈Ă��I�[�i�[�l�֒�Ă��邱�ƂŃ��C�t�T�C�N���R�X�g�̒ጸ�Ɋ�^���Ă���B
�@�ȑO�̕����ł͎�Ɍ�����̂̉��C�H�����s���Ɩ��ɏ]�����Ă������A���݂̕����ł͌����ݔ��Ǘ�����ɒS���Ă���B����܂ŐG��邱�Ƃ̏��Ȃ����������ݔ��m�����K�v�Ƃ�����ʂ������A���X�ƕς�錚���ݔ��ɃL���b�`�A�b�v�ł���悤�ɁA���ۂɌ���֓_�����s�Ȃǂ��Ȃ�����X���r���Ă���Œ��ł���B
�@�܂��A�������C�U�v��̗��Ăɂ����ẮA�����ݔ��Ǘ��ł̓���I�ȓ_���E�ێ猋�ʂ�g���u���E�̏ᗚ�������Ƃɐݔ��������A�v���p�e�B�}�l�W���[�Ɨ\�Z���܂߂����c�����{���Ȃ���A5 �N�Ȃ���10 �N�̗\�h�ۑS�I�ȏC�U�v����I�[�i�[�l�֒�Ă���B���i�����Ŋw�v��I�ۑS�̍l������ۑS���ڂ̏d�v�x���ނ̍l�����́A�v�旧�Ẵv���Z�X�̒��Ŋ������Ă���Ɗ����Ă���B
�n�[�h�ʂɂƂǂ܂�Ȃ��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎d��
�@��L�̂悤�Ȉێ��ۑS�i���Ђł͌����ێ��Ǘ��Ɩ��t���Ă���j�Ɩ����}�l�W�����g���Ă��������ŁA�N�X�[�������Ă���Ɩ��]���҂̍���E�l�ޕs���̉ۑ�ɂ��Ή����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A���̐l�ވ琬���x�̊�旧�āA�c�[����p�����ێ��Ǘ���DX���A���Ђ����i���Ă���IWMS�iIntegrated WorkplaceManagement System�j�ɂ��u�G���A����^�ێ�T�[�r�X�v�̓������i�ȂǁA���܂��܂Ȋϓ_����{���ł��o���Ȃ���ۑ�ɑΉ����Ă���B�����������q���[�}�����\�[�X�̉ۑ�ւ̑Ή���AICT �����p���Čo�c�ۑ����������Ɩ����A�o�c���l������x�����m���n���Ɛ��Y��������x������FM �̒S�������̈�ł���Ƒ����Ȃ�����X�]�����Ă���B
����̓W�]
�@�ȑO�A�t�@�V���e�B�}�l�W���[�������i�҂̐��Ƃ��Ċ�e�����Ă����������ۂɁA�u��Ƃ�FM �헪�E�v��̗��Ă⒆�����v��̎��s�Ɍg��邱�Ƃ̂ł���t�@�V���e�B�}�l�W���[���߂��������v�ƋL�ڂ����悤�ɁA�ڕW�Ƃ��铹�𒅎��ɐi��ł���Ǝ������Ă���B���l�ς̑��l���ł�萳���̂Ȃ�����ւƐi��ł��钆�ŁAFM �̗̈�͂���Ɋg�債�Ă������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ����A���̕ω��Ƀt�@�V���e�B�}�l�W���[���Ջ@���ςɑΉ��ł���悤�ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƍl���Ă���B�l�I�ɂ��A�v�E�H���ė���ێ��Ǘ��ɂƂǂ܂炸�s���Y��[�N�v���C�X�\�z�A�Ђ��Ă͌o�c�A�����A�l���AICT �Ƒ��l�ȕ�����o�����A�ω��̌������Љ�̒��ł����L���m���������Ď����\�Љ��z�^�Љ�̎����Ɋ�^�ł���t�@�V���e�B�}�l�W���[�Ƃ��Ċ��Ă��������B

�� �����}�l�W�����g�̎d��
�@���� �u�q�i������Ѓp�X�R�j

�@�͂��߂܂��āB������Ѓp�X�R�Ō����{�݃}�l�W�����g�Ɩ��ɏ]�����Ă�������Ɛ\���܂��B
�@������Ѓp�X�R�́A�n����̂����鎖�ۂ𑨂��AAI�i�l�H�m�\�j��IoT�AGIS�i�n�����V�X�e���j�A�摜�����Ȃǂ����p�����u���́E��͋Z�p�v��������3 �̗v�f��Z�����邱�ƂŁA���y����̊Ǘ��E�ۑS�A�C���t���̈ێ��Ǘ��A�ЊQ���̑��̃��X�N�Ǘ����ȂǁA�Љ�ۑ�̉����Ɍ������T�[�r�X����Ă��܂��B
�@���̂Ȃ��Ŏ����������Ă���t�@�V���e�B�}�l�W�����g�ۂł́A�k�͖k�C�������͉���܂ł̒n�������̂���Ȍڋq�Ƃ��āA�����{�𑍍݂��I�������I�ɊǗ��E�^�c�E���p���s�������{�݃}�l�W�����g�Ɋ֘A����Ɩ��x�����s���Ă��܂��B
�@�����g�́A�玙�x�ɂ����������A10 �N���g����Ă��܂����B�i�q��Ē��̓��u�̊F�l�A�ǂ�ł��������Ă������������Ⴂ�܂��ł��傤���B���݂������܂��傤�ˁI�j
�@����Ƃ��đΉ����Ă���Ɩ��͌ڋq�̉ۑ�̐��������L������̂ł����A���Ƀf�[�^�̐����E���͂ɋ��������邱�Ƃ�����A���ВT�[�r�X�ł�������{�݃}�l�W�����g�V�X�e���̉^�p�E�ێ�Ɩ���A���p�E�R�X�g���̕��́E���v�AGIS ��p�������͂Ȃǂ̋Ɩ�����ɑΉ������Ă��������Ă��܂��B���q�l��s���̕��X����݂Ă��q�ϓI�ŕ�����₷�����ʂ������ׂ��A���X����P���Ď��s������J��Ԃ��Ă��܂��B
�@������O�̂��Ƃł͂���܂����A�Ɩ��Ɋւ��n�߂������́A���g�őΉ��ł��邱�Ƃ͈̔͂������A�˘f�����Ƃ����X����܂������A�������Ɩ��o����ς݁A�����̂̂����育�Ƃɑ��āA�ǂ��������Ή��E�������@���]�܂����̂��A���q�l��ۈ��̕��X�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������y���݂Ȃ���Ɩ��ɂ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎��i�́A�֘A�Ɩ��ɏ]������ۂɎ��i�v���Ƃ��Ďw�肳��Ă��邱�Ƃ������A�֘A����̎Ј��͎𐄏�����Ă������Ƃ�����A���i�擾�Ɏ���܂����B�����́A�������܂��܂����l�O���������Ƃ�����A�m��Ȃ����Ƃ��炯�ŁA���߂ăt�@�V���e�B�}�l�W�����g�̕��̍L�����������܂����B����������ۂɖԗ��I�Ɋw���Ƃɂ���āA�����ւ��Ɩ����t�@�V���e�B�}�l�W�����g�Ƃ��Ăǂ̂悤�Ȉʒu�Â��Ȃ̂����ՓI�ɑ����邱�Ƃ��ł��A���܂��܂ȋC�Â��邱�Ƃ��ł��Ă��܂��B
�@���i���擾�������ƂŁA�g��邱�Ƃ̂ł���Ɩ��̕������X�ɍL����A�V�����Z�p�E�m�����z�����邱�Ƃ̑���������Ă��܂��B�Ɩ���玙�̖Z�����ɂ��܂��ĖY�ꂪ���ɂȂ��Ă��܂��܂����A�m���̃A�b�v�f�[�g��ӂ�Ȃ��悤�ɁA�w�т�[�߂Ȃ���A���q�l�Ɏd����C���Ă悩�����Ǝv���Ă��炦��悤�ȋZ�p�҂ɂȂ��悤�ɁA�����������X���i���Ă��������ł��B

�� ���܂���������i���𗧂Ƃ�������
�@���� �_���i���������z�[���f�B���O�X������Ёj

�@�M�҂��F��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎��i���擾�������������́A���͂��܂�J�߂�ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�ϋɓI�Ɏ擾�����킯�ł͂Ȃ��A��w�̉��t��JFMA�Ɋւ���Ă������Ƃ�����A���t�̊�𗧂Ă���x�̌y���C�����Łu�Ƃ肠��������Ă������v���炢�̂��̂������B���i�擾��2011 �N�ł��邪�A�����͌��z�v�������̈ӏ��S���i���z�v���j���������Ƃ�����A�t�@�V���e�B�}�l�W���[�̒m���⎑�i�͑S���Ƃ����ėǂ��قǎg�������Ƃ��Ȃ������B�Ƃ��낪�A���������Ŏ��i�������Ă���Ƃ������R�ŁA�����{�݃v���|�[�U���̃t�@�V���e�B�}�l�W�����g���i���L�҂Ƃ��ă`�[���ɎQ������悤�ɂȂ����B���Ȃ݂ɂ��̓����A����������500 �l�O�ゾ�������A�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[���i�҂�5�`10�l���x�������ƋL�����Ă���B���̂����肩�瓯��Ɩ����o�����Ă��������ɏ��X�Ɏ��т�������ƁA�����ƃX�L���������o���l���オ���Ă���B�Љ�S�̂��X�N���b�v���r���h����X�g�b�N�}�l�W�����g�̎���Ɉڂ�ɂ�Ė��Ԋ�Ƃ���̃j�[�Y�������A����Ɏ��������̊e������x�Ђ���t�@�V���e�B�}�l�W�����g�Ɋւ��鑊�k���邱�ƂɂȂ��Ă������B
�@�������ĕM�҂̃t�@�V���e�B�}�l�W�����g�Ɋւ���m����m�E�n�E�́A���܂����i����������Ƃ���n�܂������̂ł��邪�A���ł͂��̋��R�Ɋ��ӂ��Ă���B�M�҂��G���W�j�A�Ƃ��Ē��钼�ړI�Ȑ��ʕ��́A���z�̎{�݂�ݔ��Ɋւ��Ǘ��ƕۑS�̃m�E�n�E�ł��邪�A�����ɃR���T���^���g�Ƃ��Ē���ԐړI�Ȍ��ʂƂ��ẮA�K�Ȉێ��Ǘ��Ɖ^�c�̂��̐�ɂ���u�o�c�����̍œK���v�Ƃ������ƂɂȂ�B�������n�[�h�Ƃ��Ắu��v�ł���Ɠ����ɁA�o�c�����Ƃ����u���Y�v�ł����邱�Ƃ������ӎ�����悤�ɂȂ����̂́A�܂��ɔF��t�@�V���e�B�}�l�W���[���i���擾�������������ƌ����ėǂ��B
�@���݁A�M�҂͈ێ��Ǘ���ЂɐЂ�u���Ă��邪�A���ƊE�͐����c������������Ɍ�����������}���Ă���B���q����ɂ��l��s���A�l����̍����A�n���s�s�̐��ނȂǁA���܂Ŏ��v�̒��Ƃ��Ă����r�W�l�X���f�������A���̃G���A���m���ɏk�����Ă��Ă���B����Ɉێ��Ǘ��ƂɑS���W�̂Ȃ����Ǝ킩��̐V�K�Q�����߂������N����ƍl���Ă���B�l�Ԃɕς���ă��{�b�g�����|��x��������悤�ɂȂ�A�l�ޔh���̃l�b�g���[�N��m�E�n�E���Ȃ��Ă��A�@�탁�[�J�[�����ڋƖ��������Ƃ��ł���B�܂��A���܂ŏ����s�\�������ݔ��Ǘ���|�Ɋւ���c��ȃf�[�^��AI �ŕ��͂ł���悤�ɂȂ�AIT �n��Ƃ��Ɩ������邱�Ƃ����邾�낤�B���ꂩ��͈ێ��Ǘ��Ɋւ�������Ǘ�/ ���͂ł����Ƃ��哱�������鎞�オ�₪�ė���B�ێ��Ǘ��Ɋւ������������̂́A�������m������������Ƃ�l���������̂��̂ł͂Ȃ��Ȃ�B�u�ێ��Ǘ��Ɓv���̂͏������Ȃ��Ȃ�Ȃ����낤�B�������u�ێ��Ǘ����ƂƂ����Ёv�͂����ꓑ������A�Ȃ��Ȃ�\�����\���ɂ���B
�@���̂悤�ȏ��Ńt�@�V���e�B�}�l�W���[�́A���̒m�����g���Ċ�Ƃ������c�邽�߂̌v��𗧂ĂĂ͂ǂ����낤���B���Ƃ��A�ێ��Ǘ���Ђ͉ߋ��Ɩ��̖c��Ȑ��f�[�^�������Ă���B�p�[�g�����A���o�C�g����̑�����Ζ����ԁA�V�t�g�X�P�W���[���A�d��C���V�f���g�̔����A�P�K�⎖�̂̋N����₷���ꏊ��G��/ ���ԂȂǁA������u����v�����Ǘ�/���͂ł���Ƒ啝�ȋƖ����P���\�ɂȂ�B����ɂ͐ݔ��@��̍X�V/ �C�U�����Ƌ@�\�s�S�A�̏�X�N�Ƃ̑��֊W�A���̃f�[�^�ƃ����N�����œK�ȕۑS�v��A�ݔ��@��䒠�i�n�[�h�j�ƍ��Y�䒠�i�A�Z�b�g�j�̓������ł���ƁA�o�c�̌��������\�ɂȂ�A�Ƃ�������Ă��ł���͂��ł���B�����Ȃ�A�ێ��Ǘ��Ɩ��ɂ�����t�@�V���e�B�}�l�W���[�̖����́A����܂��܂��d�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B

�� ���̍œK�������߂�
�@���� �~�i���k�d�͊�����Ёj

�����ɗ���܂ł̓��̂�
�@���͓d�͉�Ђ̌��z����Ŏ��ЕۗL�̗V�x�{�ݗ����p��Г��̃��[�N�v���C�X���P��S�����Ă��܂��B���z����ł͔��d����Ј����������Ə��A�Б�Ȃǂ̐v�E�H���ė���ێ��ۑS����ȋƖ��Ƃ��Ă��܂����A���Ђł͌��z�Ј������̐��m�����������āA������ƘA�g���Ȃ���V�x�{�ݗ����p��[�N�v���C�X���P�ɂ����g��ł��܂��B
�@���͎����g�A���݂̉�Ђ͂R�Жڂ�2023 �N�ɒ��r�œ��Ђ��܂����B�P�Жڂ͌��݉�ЂŌ��z�̎{�H�Ǘ���6 �N�A�Q�Жڂ͓S����Ђʼnw�ɂȂǂ̊��E�v�E�H���ė���11 �N�A���̂قƂ�ǂ��������g ����h �d���ł����B�S����Ђɂ������A�V�����w���ł��Ēn��̊F����Ɋ������ŁA���̎��ӂ̏��X�X�ł͓����Ȃ̂ɃV���b�^�[���܂�A�l�̎p���Ȃ��Ƃ������i���e���Ŗڂɂ��Ă��܂����B���ꂪ���������ƂȂ�A�g���Ȃ��Ȃ����������g �����h �d�������Ă݂����ƁA�������v���悤�ɂȂ�܂����B
�@�u�n��ۑ�̉����Ɍ������V�x�{�݂̗L�����p�ł��Ȃ��̌o���E�X�L�����������Ă݂܂��H�v�B�d�C�����̃|�C���g�A�v���ׂ����ŊJ�������k�d�͂�HP �ŋ��R�L�����A�̗p�̕�W�������u�ԁA�u���ꂾ�I�v�Ǝv���]�E���邱�Ƃ����߂��̂ł����B
�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎擾
�@�]�E���邱�Ƃ����܂�A��Ђ��琬�ʂ����߂��闧��ɂȂ������ƂŁA�����Ӗ��ł̃v���b�V���[�����܂�܂����B���Ђ��@�ɂ���Ȃ�X�L���A�b�v���l�����Ƃ��A�^����Ɏv�������̂��A��W�v���̊��}���鎑�i�ɂ������u�t�@�V���e�B�}�l�W���[�v�̎擾�ł����B���i���ڂ������ׂ��Ƃ���A�����p���͂��߁A�t�@�V���e�B�̋@�\���ő�������o�����߂̕��L���m�����邱�Ƃ�������A���̕K�v���������Ď擾���邱�Ƃɂ��܂����B
�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�iFM�j�̎d��
�@�V�x�{�ݗ����p�̑Ώۂ͎�ɎБ�⎖�Ə��̋X�y�[�X�ɂȂ�܂��B�����ɐi�ޑO�ɂ́h ���p���Ă��Г��̎{�����Ɏx��͂Ȃ��i�s���͐����Ȃ��j�h �Ƃ������o�c���_�̔��f���K�v�ɂȂ�܂��B����������ɗ��Ƃ����ނƁA�܂��͎Г��ŃX�y�[�X���p�̃j�[�Y�͂Ȃ������m�F���A�Ȃ���Βn���̎����̂��Ƃɂ������������ĕ��L�Ƀj�[�Y�������s���A���p����������Ă������ƂɂȂ�܂��B����܂łɎ����S�������Č��ł́A�Г��j�[�Y�Ŏ��Ə��̋X�y�[�X�ɋߗׂ̃O���[�v��Ђ��ړ]���A�X�y�[�X�̋�襂�ݔ����̉��P�ɂȂ����������A�Б�A�p�[�g��n����Ƃ̏h�ɂƂ��Ċ��p���C�n��ۑ�̉����ɂȂ���������Ȃǂ�����܂��B���p��̈ďo���͎��R�Ȕ��z�����߂������ŁA������������邽�߂ɂ͎��ƌv��̍���A�p�r�ύX�ɔ����s���葱���A�v�E�H���A���ݎ،_��A�ێ��ۑS�Ȃnj��������čl���邱�Ƃ���������܂��B���낢��Ɠ���͂���܂����C�����̂���܂ł̌o����FM�E���z�̒m���𑍗͂��ė��p�҂⌻�n�̎Ј��ƈ�ЂƂ`�ɂ��Ă����v���Z�X�͊y�����C�v���`���Ă����d�������Ă���Ǝ������Ă��܂��B
�@�܂��A���N����͎Г��̃��[�N�v���C�X���P���S�����Ă��܂��B���Ђł́A�����̓������̑��l���A�d�����s���c�[���̕ω��A���̒��̎d�g�݂ɉ������Ɩ����e�̕ω��Ȃǂ���A���[�N�v���C�X�̂���������������Ⴊ�����Ă��܂��B�d���̐������قȂ�e���傩��̗v�]�i�d���̂��₷���j����{�R���Z�v�g�̃��C�A�E�g�ɂǂ����Ƃ�����ł������A���s���낵�Ȃ�����u�����œ��������v�Ǝv����悤�ȃ��[�N�v���C�X�𗘗p�҂ƈꏏ�ɂ��肠���邱�Ƃ�ڎw���Ď��g��ł���Ƃ���ł��B
�Ō��
�@�V�x�{�ݗ����p�E���[�N�v���C�X�Ƃ��A���̐����͈�ł͂���܂���B���p�҂Ɖ��x������Ęb���A���i�`�[���ňӌ����o�������A��������ĊW�҂݂�ȂŁw�œK���x������Ă������̂��Ǝv���Ă��܂��B�������̓���I�Ƃ��̂悤�ɁA���x��FM ��ʂ��Ă݂�ȂƁu���ꂾ�I�v�Ǝv����u�Ԃ����L���Ȃ���C�t�@�V���e�B�����@�\���ő�������o���Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�@���͓d�͉�Ђ̌��z����Ŏ��ЕۗL�̗V�x�{�ݗ����p��Г��̃��[�N�v���C�X���P��S�����Ă��܂��B���z����ł͔��d����Ј����������Ə��A�Б�Ȃǂ̐v�E�H���ė���ێ��ۑS����ȋƖ��Ƃ��Ă��܂����A���Ђł͌��z�Ј������̐��m�����������āA������ƘA�g���Ȃ���V�x�{�ݗ����p��[�N�v���C�X���P�ɂ����g��ł��܂��B
�@���͎����g�A���݂̉�Ђ͂R�Жڂ�2023 �N�ɒ��r�œ��Ђ��܂����B�P�Жڂ͌��݉�ЂŌ��z�̎{�H�Ǘ���6 �N�A�Q�Жڂ͓S����Ђʼnw�ɂȂǂ̊��E�v�E�H���ė���11 �N�A���̂قƂ�ǂ��������g ����h �d���ł����B�S����Ђɂ������A�V�����w���ł��Ēn��̊F����Ɋ������ŁA���̎��ӂ̏��X�X�ł͓����Ȃ̂ɃV���b�^�[���܂�A�l�̎p���Ȃ��Ƃ������i���e���Ŗڂɂ��Ă��܂����B���ꂪ���������ƂȂ�A�g���Ȃ��Ȃ����������g �����h �d�������Ă݂����ƁA�������v���悤�ɂȂ�܂����B
�@�u�n��ۑ�̉����Ɍ������V�x�{�݂̗L�����p�ł��Ȃ��̌o���E�X�L�����������Ă݂܂��H�v�B�d�C�����̃|�C���g�A�v���ׂ����ŊJ�������k�d�͂�HP �ŋ��R�L�����A�̗p�̕�W�������u�ԁA�u���ꂾ�I�v�Ǝv���]�E���邱�Ƃ����߂��̂ł����B
�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[�̎擾
�@�]�E���邱�Ƃ����܂�A��Ђ��琬�ʂ����߂��闧��ɂȂ������ƂŁA�����Ӗ��ł̃v���b�V���[�����܂�܂����B���Ђ��@�ɂ���Ȃ�X�L���A�b�v���l�����Ƃ��A�^����Ɏv�������̂��A��W�v���̊��}���鎑�i�ɂ������u�t�@�V���e�B�}�l�W���[�v�̎擾�ł����B���i���ڂ������ׂ��Ƃ���A�����p���͂��߁A�t�@�V���e�B�̋@�\���ő�������o�����߂̕��L���m�����邱�Ƃ�������A���̕K�v���������Ď擾���邱�Ƃɂ��܂����B
�t�@�V���e�B�}�l�W�����g�iFM�j�̎d��
�@�V�x�{�ݗ����p�̑Ώۂ͎�ɎБ�⎖�Ə��̋X�y�[�X�ɂȂ�܂��B�����ɐi�ޑO�ɂ́h ���p���Ă��Г��̎{�����Ɏx��͂Ȃ��i�s���͐����Ȃ��j�h �Ƃ������o�c���_�̔��f���K�v�ɂȂ�܂��B����������ɗ��Ƃ����ނƁA�܂��͎Г��ŃX�y�[�X���p�̃j�[�Y�͂Ȃ������m�F���A�Ȃ���Βn���̎����̂��Ƃɂ������������ĕ��L�Ƀj�[�Y�������s���A���p����������Ă������ƂɂȂ�܂��B����܂łɎ����S�������Č��ł́A�Г��j�[�Y�Ŏ��Ə��̋X�y�[�X�ɋߗׂ̃O���[�v��Ђ��ړ]���A�X�y�[�X�̋�襂�ݔ����̉��P�ɂȂ����������A�Б�A�p�[�g��n����Ƃ̏h�ɂƂ��Ċ��p���C�n��ۑ�̉����ɂȂ���������Ȃǂ�����܂��B���p��̈ďo���͎��R�Ȕ��z�����߂������ŁA������������邽�߂ɂ͎��ƌv��̍���A�p�r�ύX�ɔ����s���葱���A�v�E�H���A���ݎ،_��A�ێ��ۑS�Ȃnj��������čl���邱�Ƃ���������܂��B���낢��Ɠ���͂���܂����C�����̂���܂ł̌o����FM�E���z�̒m���𑍗͂��ė��p�҂⌻�n�̎Ј��ƈ�ЂƂ`�ɂ��Ă����v���Z�X�͊y�����C�v���`���Ă����d�������Ă���Ǝ������Ă��܂��B
�@�܂��A���N����͎Г��̃��[�N�v���C�X���P���S�����Ă��܂��B���Ђł́A�����̓������̑��l���A�d�����s���c�[���̕ω��A���̒��̎d�g�݂ɉ������Ɩ����e�̕ω��Ȃǂ���A���[�N�v���C�X�̂���������������Ⴊ�����Ă��܂��B�d���̐������قȂ�e���傩��̗v�]�i�d���̂��₷���j����{�R���Z�v�g�̃��C�A�E�g�ɂǂ����Ƃ�����ł������A���s���낵�Ȃ�����u�����œ��������v�Ǝv����悤�ȃ��[�N�v���C�X�𗘗p�҂ƈꏏ�ɂ��肠���邱�Ƃ�ڎw���Ď��g��ł���Ƃ���ł��B
�Ō��
�@�V�x�{�ݗ����p�E���[�N�v���C�X�Ƃ��A���̐����͈�ł͂���܂���B���p�҂Ɖ��x������Ęb���A���i�`�[���ňӌ����o�������A��������ĊW�҂݂�ȂŁw�œK���x������Ă������̂��Ǝv���Ă��܂��B�������̓���I�Ƃ��̂悤�ɁA���x��FM ��ʂ��Ă݂�ȂƁu���ꂾ�I�v�Ǝv����u�Ԃ����L���Ȃ���C�t�@�V���e�B�����@�\���ő�������o���Ă��������ƍl���Ă��܂��B

�� �{�З��ւ��v���W�F�N�g���@�Ɏ��i���擾�B
�@�@FM�́A���Ɖ�Ђ̒S���҂ɕK�{�̒m��
�@�|�� �C�L�i������Ђ��悬��z�[���f�B���O�X�j

�@�����Ζ�����u���悬��z�[���f�B���O�X�v�͈��Q�����R�s�ɖ{�Ђ�u����ƃO���[�v�ŁA���̎P���ɁA�ɗ\��s���͂��߂Ƃ���O���[�v11 �Ђ�L���A�n��o�ϥ�Y�Ƃ̎����I�Ȕ��W�ɍv�����ׂ����ƓW�J���Ă���܂��B
�@���Ђ̖{�Ќ�����1952�N�̏v�H��70�N�ȏオ�o�߂��A�V�������Ă���܂����̂ŁA2022�N8���ɖ{�Ќ��ւ����肵�A�Ȍ�A���͖{�Ќ���PT(�v���W�F�N�g�`�[��)�Ƃ��āA�e��v���W�F�N�g�̊�楐��i��S���Ă���܂��B
�@�F��FM�̎��i�擾�̗��R�ł����A�������ɒ��C����܂ł͉c�ƓX�o�������Ȃ��A���z�́u���v�̎���������Ȃ��f�l�ł������A�}篁A�{�Ќ��փv���W�F�N�g�iPJ�j�Ɍg��邱�ƂɂȂ�܂����B���ł��o���Ă��܂����A�v��{�H�����S�����������Ă���|���H���X�Ƃ̉�c�ɏ��߂ďo�Ȃ����ۂɁu���[�N�v���C�X�H�G���W�j�A�����O���|�[�g�H�������f�f�H�c�S���Ӗ����������c�v�Ǝv�������Ƃ��AFM�̕����n�߂����ړI�ȓ��@�ł����B�����̓s���A��FM �Ɋւ���m���擾���ړI�ŁA���i�擾�܂ōl���Ă���܂���ł������APJ��i�߂钆�ł���������̖��h�Ɂu�F��t�@�V���e�B�}�l�W���[�v�̋L�ڂ�����A�����g���擾����A�W�҂̕��Ƃ̋��ʂ̘b�肪�ł���̂ł́H�Ǝv���A���i�擾��ڎw��������ł��B
�@FM���i��m���̎d���ւ̊��������ɂ��āA�E�����u���i�v�͕K�{�ł͂���܂���̂Œ��ړI�ɂ͊W�Ȃ����̂́A������Y��ނȂǂ̃n�[�h�ʂɂ��Ă͎Г��̊e�l����ƌ��������Ă���܂��̂Ŏ�X���܂��܂Ȃ��ӌ��Ղ��邱�Ƃ������A���̂悤�Ȏ��Ɂu���̒��ɂ̓t�@�V���e�B�}�l�W�����g�Ƃ����T�O������A���͂��̕������Ď��i������Ă���̂ł����c�v�Ƃ���������t���Đ����������܂��ƁA���O�ɂ����𥂲���͂����������܂����̂ŁA���������Ӗ��ł͖��ɗ��������Ǝv���Ă���܂��B
�@FM�́u�m���v�Ɋւ��ẮA�|���H���X�͂��ߊe���c���Ǝ҂Ƌ��c���鎞�����łȂ��A�Г����������쐬��������s���ۂɂ��傢�ɖ𗧂��܂����B���R�AFM�̒m���́A�ЊO�̊F�l�̐��̈�Ƃ͈قȂ�܂��̂ŁA�ڍׂɂ��Ă̓v���ɂ��C�����邱�ƂɂȂ�܂����A�������ǂ������R���Z�v�g�Ō��Ă邩�A�����₷�������ǂ����邩�A�ǂ������X�P�W���[����PJ��i�߂邩���X�A�܂���FM�̒m�������邱�ƂŊW�҂̊F�l�Ɓu���ʌ���v�Řb�����邱�Ƃ��ł����Ƃ����Ӗ��ł́A���Ɖ�Ђ̌��z��Ǎ����Ɍg���S���҂Ƃ��Ă͕K�{�̒m�����Ɨ������Ă���܂��B
�@�܂��A�Г������̘b�ł��ƁAPJ��i�߂钆�ŁA�R���i�Ђ╨���㏸�Ȃǂ̎Љ����ς��܂��̂ŁA����ɔ����A�V�{�ЂɊւ���c�_���ω����܂����i�����[�g���[�N���y�ɂ�鏰�ʐϕs�v�_��\�Z�Δ�ł̃R�X�g�_�E�������Ȃǁj�A���̓s�x�u�����͐V�{�Ђɉ������߁A������ɂ͉��������������̂��H�v�Ƃ����ړI�m�ɂ��邱�Ƃ��ł����̂́AFM�̑̌n�I�Ȓm��������������ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�@���Ђ̖{�Ќ���PJ�͌��ݒn��2�����ւ����s������2022�N�`2029�N�̒�����ƂȂ�A�����̐i�����Ƃ��Ă�20�`30���Ƃ������ł����A2025�N�t�ɂ�1 ���ڂ��������܂��̂ŁA���܂Ŋ�悵�Ă������Ƃ����ۂɎ�����蒅������t�F�[�Y�ɓ���܂��B�z��ʂ�Ɏ����ł��邱�Ƃ�����A����ŁA��肭�蒅�ł��Ȃ����̂�z��O�̎��ۂ��������邾�낤�Ɗo��͂��Ă���܂����A���̓s�x�AFM�̊w�K��ʂ��ē����m�������p���āA�V�{�Ђ̉^�p���`���[�j���O���A2���ڂ̐v��{�H�v����W�҂̊F�l�ƂƂ��ɂ���ɖ����グ�A�]�ƈ��S���ɖ������ĖႦ��悤�ȐV�{�Ђ�����グ�����ƍl���Ă���܂��B